プロダクト・レッド・グロースを読んだ
「プロダクト・レッド・オーガニゼーション」の背景にある「プロダクト・レッド・グロース」モデルについて先に知っていると、後日、前者を読んだときにより理解が進むような気がしたので本書を読んだ。
分野的にはプロダクトマネジメント関連の書籍と近いところがあると感じたが、基本的にはビジネス側からの視点なので、プロダクト側からだけではない視点を増やすためにも読んでみてよかったなと思う。
プロダクト・レッド・グロースモデル
本書ではプロダクト・レッド・グロース(以下、PLG)モデルについて紹介・説明している。これは表紙の言葉を借りれば「プロダクトでプロダクトを売る」ビジネスモデルだ。本文中ではプロダクト主導型ビジネスモデルと訳されている。
セールス主導型ビジネスモデルと比較しながら、PLGモデルが適するビジネスの類型や、適用するにあたって重要なポイントなどを紹介している。
この本の中で私がなるほどと思ったポイントのひとつが「ビジネスのインプットとアウトプットを知る」という部分だ。
「第12章 最適化プロセスを開発する」の中で持続的な成長を実現するためのプロセスとして「トリプルAスプリント」というものを紹介している。このプロセスにおいて外すことができないものがビジネスに必要なアウトプット(ARRなど)を生み出すインプット(展示会、広告、eメールマーケティング)が何かを理解することだとしている。
どんなインプットが望むアウトプットを生み出しているか理解していなければ、持続的な成長を実現することはできない。なるほど確かにそうかもしれない。これまでを振り返ってみるとインプットに対する理解があまりない状態でアウトプットについて考えていることが多かったように思う。言うは易く行うは難しかもしれないが押さえておくと役に立つ考え方だと感じた。
余談
少し前にmasuidriveさんのこのツイートがバズっていた。
「そうよねー」でもあるし「とはいえ、立場の違う人間にとっては難しいよねー」でもあると思っている。後者は特に「理解がある経営陣」という部分についてなのだが、エンジニアの評価って例えば売上(利益)みたいな多くの経営陣にとってわかりやすい指標からは多分算定しづらいのですよね。。。エンジニアが会社を選ぶときに評価をするのは年収以外に「事業ドメイン」「技術スタック」と共に「理解がありアホなこと言わない上司、経営陣」と「適切な成長機会」があると思う
— masuidrive (@masuidrive) February 9, 2022
特にアホに説明する心理コストは高いから、なぜメモリがたくさんいるのかとか、この機能の変更は大変なのかとか
じゃあどうするんだというと、どうやら売上(利益)というのはプロダクトを作ってビジネスをしようとする組織にとってあんまり適切な指標じゃなさそうだぞ、というのが「プロダクト・レッド・オーガニゼーション」で語られている話の一部であるらしい。
これが冒頭に書いたfukabori.fm 62. プロダクト・レッド・オーガニゼーションで話していた「先行指標と遅行指標」という話(という理解)。
またちょっと話が変わるけど例えばエンジニア採用でも理解のある経営陣というのは重要そうだ。近年のエンジニア採用はえげつない難易度になっていて、オファーできる金額の優位性で戦えることは少ないと思う。そのなかでビジネス上でもエンジニアが必要とされ評価される環境だよ、気持ちよく働くことができるよという感情面・社会面での報酬が期待できることはひとつの優位性だ。理解のある経営陣というのはそれを現す指標のひとつとして私は見ている。
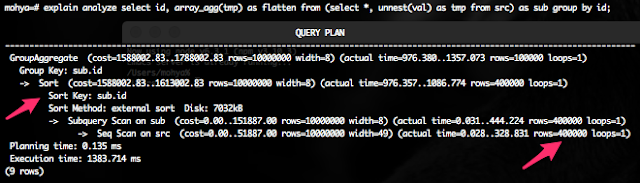


コメント
コメントを投稿